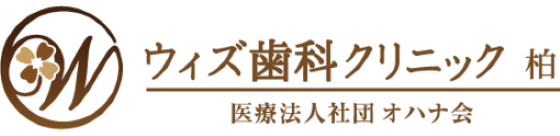子どもが歯医者を怖がるときは?上手に通えるようになるコツ

皆さん、こんにちは!イオンモール柏の向かいにあるウィズ歯科クリニックの日本小児歯科学会専門医の根本です。
小さなお子さまが歯医者を怖がってしまうのは、決して珍しいことではありません。初めての経験に対する不安や、過去の痛い思い出が影響して「行きたくない」と泣いてしまうことも。ですが、歯科医院はむし歯や歯茎のトラブルを予防し、健康なお口を育てるために欠かせない場所です。
本コラムでは、子どもが歯医者に行きたがらないときの対応や声かけのコツ、トラウマを防ぐ方法、小児歯科治療における医院選びのポイントについて、歯科医師の視点から丁寧に解説します。保護者の方が安心してお子さまを連れていけるようになるヒントとして、ぜひお役立てください。
子どもが歯医者を怖がる理由

● 過去の痛みや処置の記憶による条件づけ
お子さまが歯科医院に対して恐怖心を抱く背景には、古典的条件づけ(Pavlov型条件づけ)の影響が考えられます。過去にむし歯治療や麻酔時に痛みを経験した場合、「歯医者」という環境そのものが、痛み=恐怖の記憶と結びつくのです。特に小児期は記憶の定着が感情に左右されやすく、恐怖を伴う記憶は偏桃体(扁桃体)に強く刻まれやすいとされます。
また、歯科用ハンドピースの高周波音や局所麻酔時の刺入刺激など、感覚的に強い刺激は感覚記憶を通じて長期記憶に残りやすいため、1度の体験でも「怖い場所」という印象が強固に形成されることがあります。
● 五感を通じた環境刺激による緊張
歯科医院では、消毒薬のにおい(例:グルコン酸クロルヘキシジンなど)や金属音、ライトのまぶしさなど、子どもにとって普段経験しない五感刺激が多く存在します。これらの感覚刺激が複合的に加わることで、自律神経系が過敏に反応し、交感神経優位(いわゆる“戦うか逃げるか”反応)となり、心拍数の上昇や筋緊張、落ち着きのなさを招くことがあります。
さらに、「白衣高血圧」と呼ばれる現象は小児でも見られ、医療者の服装や院内の雰囲気が不安感を誘発する原因になると指摘されています。
● 治療内容が分からないことへの不安
子どもは未知への恐怖に非常に敏感です。事前の十分な説明がないまま診療を開始すると、「何をされるかわからない」「痛いことをされるかもしれない」といった予期不安が高まり、自律神経系やホルモン反応(アドレナリン分泌)を通じて生理的ストレス反応を引き起こすことがあります。
このような心理的緊張は、診療中の協力度の低下や過呼吸、涙や汗などの身体反応にもつながることがあり、診療の継続自体が難しくなるケースもあります。
● 保護者の不安や緊張の影響
お子さまは、保護者の感情を敏感に読み取ります。特に3〜6歳頃の子どもは、“情動の共鳴”が強く働くため、保護者が不安そうにしていると、その感情がミラーニューロンを介して子どもに伝わり、「ここは怖い場所なんだ」と思い込む要因になります。
このように、お子さまの歯科恐怖症の背景には、家庭内の言動や雰囲気も密接に関係しています。保護者が過去の歯科体験を「痛かった」「怖かった」と口にするだけでも、子どもはその情報を記憶し、“二次的恐怖(vicarious fear)”として学習してしまうことがあります。
子どもが歯医者に行きたがらないときの対応

● 歯医者に行く前の声かけ
お子さまに「怖くないよ」と言い聞かせるだけでは、かえって不安を助長する場合があります。心理学的には、子どもの不安を否定するのではなく共感し、安心できる言葉で導くことが大切とされています。たとえば、「ちょっとドキドキするよね。でも先生がやさしく見てくれるよ」「一緒にお口をきれいにしてもらおうね」といったポジティブで共感的な声かけは、情緒の安定に寄与します。
また、「泣いたらだめ」と禁止するよりも、「頑張れたら、先生もママも嬉しいよ」と行動に対する肯定的なフィードバックを意識することで、お子さまの達成感や自尊感情が育ちやすくなります。これは正の強化(positive reinforcement)と呼ばれ、子どもの行動修正に有効とされる心理的アプローチです。
● 歯医者に行くときの事前説明の方法
年齢や発達段階に応じたわかりやすい説明も重要です。たとえば3歳前後の幼児では、抽象的な説明よりも、視覚的情報(絵本や歯科動画)を用いた具体的なイメージ形成が有効とされています。「先生が小さな鏡でお口の中を見るよ」「機械でシャカシャカって音がするけど、お掃除の音だよ」など、事前に体験の予告をすることで予測可能性を高め、恐怖心を軽減できます。
医学的には、「予測可能性が高い状況では、痛みや不安の知覚が軽減される」という研究もあり、適切な事前説明は“痛みの閾値”にも影響を与える可能性があると考えられています。
● 約束を守ることが信頼につながる
お子さまに対して「今日は見るだけ」と伝えた場合、必ずその通りにすることが信頼関係を築く基本です。発達心理学の観点でも、一貫性と予測可能性が安心感につながるとされており、これを損なうと「歯医者は信用できない」という印象が強く残ります。たとえば、診察中に急な処置が必要になった場合は、保護者と連携し、お子さまへの説明と同意を得たうえで進めることが望ましいです。
● 付き添いの姿勢もポイント
治療中、保護者の方が穏やかで安心感のある態度を示すことは、子どもにとって大きな心の支えになります。特に、親子間で形成される“安全基地(secure base)”という概念に基づき、そばに安心できる大人がいることで、お子さまは新しい環境にも適応しやすくなります。
一方で、治療中に保護者が過度に緊張したり、押さえつけたり、叱責したりすると、その緊張が子どもに伝わり、交感神経が優位になって恐怖反応を引き起こしやすくなるため、避けるべきです。笑顔で手を握る、視線を合わせるなどの安心のジェスチャーが有効です。
歯医者がトラウマになるのを予防する方法

● 初診は「慣れるため」に利用する
初めての歯科医院では、診察台に座るだけ、器具を見せるだけ、お口を覗いて終わりなど、治療を目的にせず「慣れる時間」として使うことが、トラウマ予防につながります。無理な治療は避け、段階的に信頼関係を築いていくことが理想です。
● 無理に治療を進めない
嫌がるお子さまを押さえつけて治療を行うと、恐怖心だけが残り、その後の通院が困難になるケースが少なくありません。特に乳歯の治療は、無理をせずタイミングを見て行うのが望ましいです。
● スモールステップで成功体験を積む
「診察台に座れた」「お口を開けられた」など、小さな成功体験を積み重ねることで自信が生まれ、自然と治療への抵抗感が減っていきます。歯科医師やスタッフからの「えらかったね!」という言葉が、お子さまのモチベーションアップに直結します。
子どもが楽しいと思える歯医者の特徴
● 子どもに寄り添った診療姿勢
子どもの気持ちに寄り添って対応してくれる小児歯科治療の専門医院では、痛みの少ない処置や声かけの工夫が徹底されています。ゆっくり話を聞いてくれる医師・スタッフが揃っていることが安心材料になります。
● キッズスペースや遊具の充実
待ち時間も楽しく過ごせるように絵本やおもちゃ、テレビモニターなどが備えられた環境は、歯科医院に対する良いイメージづくりに役立ちます。「遊べる場所」という印象があるだけでも、お子さまの心のハードルはぐっと下がります。
● ごほうびシステムがある
治療後に小さなごほうび(シールやおもちゃ)をもらえる仕組みがあると、お子さまのやる気や達成感につながります。「頑張ったらシールもらえるよ」という明確な目標が、治療への前向きな気持ちを後押しします。
● 医院全体が子どもに優しい雰囲気
白衣ではなくカラフルなユニフォーム、優しい表情で話しかけてくれるスタッフ、BGMのある空間など、医院全体の雰囲気がやわらかいことも、お子さまにとっての安心材料となります。
まとめ
子どもが歯医者に行きたがらないのは、不安や恐怖が原因であることがほとんどです。保護者の方の声かけや事前説明の工夫、歯科医院の診療方針や雰囲気によって、歯医者は「怖い場所」から「安心できる場所」へと変わります。無理をさせず、少しずつ慣れていくステップが、トラウマの予防にもつながります。ウィズ歯科クリニックでは、お子さま一人ひとりの気持ちに寄り添いながら、小児歯科治療を丁寧に進めています。歯医者嫌いを克服したいとお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
千葉県柏市のウィズ歯科クリニックでは小児歯科専門の医師が在籍しております。お子さまのお口のお悩みがございましたらお気軽にご相談ください。
技術・接遇の追求
患者満足度日本一の歯科医院を目指します
『一般歯科』『小児歯科』『口腔外科』『親知らずの抜歯』『矯正歯科』『審美』『歯周病治療』『口臭治療』『入れ歯』『歯の痛み』『無痛治療』『ホワイトニング』『インプラント』『フラップレスインプラント』『セラミック治療』『保育士託児』『相談室でのカウンセリング』『口コミ、評判』『分かりやすい説明』
柏、南柏の歯医者 ウィズ歯科クリニック 柏院
オフィシャルサイト:https://www.with-dc.com/
インプラントサイト:https://www.with-dc.com/implant/
お問合せ電話番号:04-7145-0002