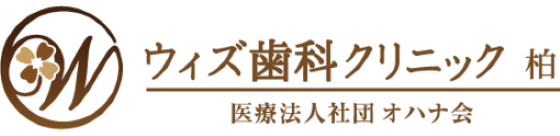舌がハート型?舌小帯の影響かもしれません

皆さん、こんにちは!イオンモール柏の向かいにあるウィズ歯科クリニックの日本小児歯科学会専門医の根本です。
お子さまやご自身の舌先が「ハート型」に見えると気づいたことはありませんか?これは舌小帯という舌の裏側にある膜の短さが影響している可能性があります。「舌が短い」「うまく発音ができない」「授乳がうまくいかない」といったトラブルの背景に、舌小帯の異常が隠れていることがあります。この記事では、いわゆる「ハート舌」の特徴や舌小帯のチェック方法、切除が必要になるケース、さらに発音や授乳への影響について、歯科医師の視点から詳しく解説いたします。お子さまの発達や日常生活にかかわる大切なテーマですので、ぜひ最後までご覧ください。
舌小帯が短いハート舌とは?
舌小帯(ぜっしょうたい)は、舌の裏側に位置する粘膜性のひだで、舌下面と口腔底(舌の付け根の内側)をつなぐ帯状の組織です。この構造は、舌の位置や可動範囲を適切に保つうえで重要な役割を担っています。通常、舌小帯には一定の柔軟性と長さがあり、舌を前方や上方へ自由に動かすことが可能ですが、先天的にこの舌小帯が短い、または厚く緊張している場合には、舌の動きに制限が生じます。
このような状態は、医学的には舌小帯短縮症(ankyloglossia)と呼ばれ、日本語では「短舌症」とも表現されます。舌小帯短縮症のある方が舌を前に突き出すと、舌先が中央で引き込まれ、ハートのような形に見えることがあり、これが俗に「ハート舌」と呼ばれるゆえんです。ハート舌は見た目で気づかれることが多く、乳幼児健診や授乳時、または発音指導の場面などで指摘されるケースもあります。
舌小帯のチェック方法は?

舌小帯の異常は、家庭でもある程度チェックすることが可能です。以下のポイントを確認してみてください。
◎ご自宅でできる簡単なチェック方法
・舌で上唇を舐めることができるか
・舌を前に出したときの形を見る
舌を真っすぐ前に出すとき、舌先がV字型、もしくはハート型に分かれて見える場合もチェックポイントです。
・発音の発達の遅れを観察
幼児期に特定の音が言いにくい、「ら行」がうまく言えない、「た・さ・な」など舌を使う音が不明瞭な場合、舌小帯の動きが関係していることがあります。
・授乳中の様子を見る(乳児の場合)
吸い付きが弱い、ミルクを飲むのに時間がかかる、母乳を飲んだ後でも満足しない様子が続くなども舌小帯が短いことによる影響かもしれません。
◎歯科・小児科での精密な診断が必要
自宅でのチェックで気になることがあった場合は、歯科や小児科での診察をおすすめします。専門家による視診や舌の可動域検査を通じて、必要に応じて外科的な治療を検討します。
舌小帯の切除が必要なケース

舌小帯が短い場合でも、すべてのケースで外科的処置が必要になるわけではありません。舌の可動域に明らかな制限がなく、日常生活や発達に支障が認められない軽度の短縮であれば、経過観察で対応することが一般的です。
しかしながら、哺乳・構音・摂食嚥下機能・顎顔面の成長発育などに明らかな影響が認められる場合には、舌小帯形成術や切除が検討されます。
◎舌小帯切除が推奨される主なケース
・新生児・乳児期の哺乳困難
舌の前方運動が制限され、乳首をしっかりとくわえられずに吸着不良を起こすことがあります。結果として、哺乳量の不足、体重増加不良、乳頭の痛みや乳腺炎のリスクが母子双方に発生します。母乳育児支援を行う助産師や小児科医との連携のうえ、評価が必要です。
・幼児期以降の発音障害(構音障害)
「ラ行」「サ行」「タ行」など舌尖音の発音に障害がみられる場合、舌小帯による可動制限が影響していることがあります。言語聴覚士(ST)による構音評価で治療適応が明確になることもあり、外科的介入と並行して言語訓練が行われるケースがあります。
・摂食・嚥下機能への影響
舌が口腔内で適切に動かないことで、咀嚼や嚥下動作に支障が出ることがあります。食事に時間がかかる、飲み込みにくいなどの症状がある場合には、機能的観点から切除が検討されます。
・歯列や顎の成長への影響
舌の低位(舌が下に沈んだ状態)は、上顎骨の発育不足や歯列不正(開咬や叢生など)に関連することが報告されています。成長期の骨格発育や歯列矯正治療に悪影響を及ぼすリスクがある場合、早期の介入が推奨されることもあります。
◎舌小帯切除術の概要と注意点
舌小帯の手術には主に2つの方法があり、状態や年齢によって選択されます。
舌小帯切除術:比較的単純な膜状の小帯を切開する方法。乳児では無麻酔で行われることもあります。
舌小帯形成:筋線維が関与するなど、より強固な小帯の場合に選択される方法で、局所麻酔下に切開・縫合を伴います。縫合部の形態を整えることで、再癒着のリスクを下げます。また、レーザーや電気メス(電気凝固)を使用する低侵襲な方法も普及しており、出血や術後疼痛が少ないのが特徴です。ただし、術式選択は症例ごとに異なり、医師の判断が必要です。
◎術後ケアと再癒着の予防
切除後は、傷の治癒過程で再癒着(再付着)を防ぐために、舌の可動訓練が重要です。舌のストレッチや舌先運動のリハビリ(いわゆるMFT:口腔筋機能療法)を、数週間継続して行います。言語聴覚士や歯科衛生士の指導のもと、日常生活に取り入れやすい訓練方法が提案されます。舌小帯切除は比較的安全性の高い処置とされていますが、手術の適応、方法、術後のケアまでを総合的に評価し、慎重に進めることが重要です。
舌小帯による発音障害や授乳への影響

舌小帯が短い状態は、「見た目の問題」だけにとどまらず、乳児期から幼児期にかけての発達に大きく関与することがあります。特に注意すべきなのが、新生児・乳児期の授乳障害と幼児以降の発音障害です。これらはご家庭での観察から気づかれることも多く、早期対応が望ましいとされています。
◎授乳への影響
正常な授乳には、舌を使った「波打つような動き」による陰圧の形成が不可欠です。この動きにより、乳首を口腔内に保持し、効率的な哺乳が可能となります。しかし、舌小帯が短いと舌の可動域が制限され、舌の前方運動や持ち上げが困難になります。結果として、以下のような問題が現れることがあります。
・吸着が不十分で、頻繁に乳首から離れてしまう
・授乳時間が極端に長くなる、または飲み残しが多い
・乳児の体重増加が緩慢になる
・母親が乳頭の痛みや炎症を訴えることがある
これらは、哺乳不全(nipple feeding dysfunction)の一因としても指摘されており、母乳育児を行うご家庭にとって大きなストレスとなり得ます。授乳に関して気になる様子がみられる場合は、小児科や歯科口腔外科、小児歯科などで舌小帯の状態を確認することが推奨されます。
◎発音障害への影響
舌は発音において極めて重要な役割を担う器官です。とくに「ラ行」「サ行」「タ行」など、舌先の微細な動きが求められる音を正確に発音するためには、十分な舌の可動性が必要となります。舌小帯が短いと、次のような影響が考えられます。
・舌先を口蓋側に持ち上げる動作が困難になる
・舌尖音が不明瞭になり、言葉の聞き取りがしにくくなる
・話すことへの自信の低下や対人関係への影響
このような発音障害は、言語発達に影響を及ぼすだけでなく、就学以降の集団生活でもコミュニケーションの壁となる場合があります。発音に不安があるお子さまの場合、歯科医師や言語聴覚士(ST)による評価が有効です。必要に応じて、舌小帯の切除術と、術後の舌機能訓練(口腔筋機能療法:MFT)を組み合わせて行うことで、発音の改善が期待されます。
まとめ
「ハート舌」と呼ばれる舌小帯が短い状態は、見た目だけでなく授乳や発音などお子さまの日常生活に大きく関わる可能性があります。早期に気づき、正しいチェック方法を知ることで、必要な対応が可能になります。切除が必要なケースもありますが、医師の判断とともに慎重に検討されるべきです。
千葉県柏市のウィズ歯科クリニックでは小児歯科専門の医師が在籍しております。お子さまのお口のお悩みがございましたらお気軽にご相談ください。
技術・接遇の追求
患者満足度日本一の歯科医院を目指します
『一般歯科』『小児歯科』『口腔外科』『親知らずの抜歯』『矯正歯科』『審美』『歯周病治療』『口臭治療』『入れ歯』『歯の痛み』『無痛治療』『ホワイトニング』『インプラント』『フラップレスインプラント』『セラミック治療』『保育士託児』『相談室でのカウンセリング』『口コミ、評判』『分かりやすい説明』
柏、南柏の歯医者 ウィズ歯科クリニック 柏院
オフィシャルサイト:https://www.with-dc.com/
インプラントサイト:https://www.with-dc.com/implant/
お問合せ電話番号:04-7145-0002